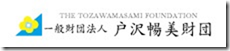会社設立時に活用できる補助金・助成金~活用する際の注意事項についても解説~
会社設立時や創業初期によくある課題として「資金調達」が挙げられます。融資では実績が審査対象となり、立ち上げすぐだと上手くいかないケースが多いためです。そこで可能なら国や自治体が提供する補助金・助成金の活用も検討してみましょう。
創業期に申し込める制度は限られていますが、それでもいくつか利用できるものがあります。
ここではその例を紹介するとともに、活用する際の注意事項についても解説していきます。
小規模事業者持続化補助金(創業型)
「小規模事業者持続化補助金(創業型)」は、創業後3年以内の小規模事業者が自ら策定した経営計画に基づき販路開拓や業務効率化などに取り組む際、かかる費用について国が支援を行うとする補助金のことです。販路開拓等にかけた広告宣伝費、設備費、開発費などさまざまな費用の一部について支援が受けられます。
補助上限は「200万円(インボイス特例事業者は最大250万円)」、補助率は「2/3」となっています。
申請には「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書が必要で、商工会・商工会議所の支援を受けながら事業計画を作成することも求められます。
小規模事業者持続化補助金の公募情報等はこちらの公式HPから確認可能です。
ものづくり補助金
「ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)」とは、中小企業や小規模事業者が革新的な製品・サービスの開発や生産性向上、海外展開などに取り組んだ際、そこに要した設備投資やシステム導入の費用を国が支援するとする補助金制度です。
補助上限額は「最大3,000万円※」、補助率は「中小企業1/2」、「小規模事業者2/3」で、申請枠によって異なります。
※申請枠によって補助上限額は異なる。
申請には事業計画書の作成と、電子申請システム(Jグランツ)を利用するためのGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。製造業だけでなく、商業やサービス業も対象となっており、創業間もない事業者でも申請可能です。
また、最低賃金引き上げに取り組む場合は補助率が優遇されるなど、成長意欲のある事業者にとって有効な制度といえるでしょう。
ものづくり補助金については、事務局である全国中小企業団体中央会が運用しており、こちらのサイトから最新情報が確認できます。
起業支援金(地方創生起業支援事業)
「起業支援金(地方創生起業支援事業)」は、地域課題の解決に資する社会的事業を新たに起業する個人や法人を対象とした支援制度です。
補助上限額は「200万円」、補助率は「1/2以内」で、人件費・事務所賃借料・設備費・広報費など幅広い経費が支援対象となります。
支給決定後は、都道府県が選定した支援団体による「伴走支援(メンタリングや経営相談等)」を受けられるのが特徴です。
実施の有無や要件、受付期間は都道府県ごとに異なるため、申請を検討する際は必ず該当自治体の最新情報を確認してください。
なお、実施するのは全国の自治体ですが、制度自体は内閣府地方創生推進事務局が主導しておりその内容もこちらのサイトから確認できます。
地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)
「地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)」は、中小機構と都道府県、金融機関等が共同で設立したファンドの運用益を活用し、創業や新規事業展開に取り組む中小企業や創業者を助成する制度です。
対象となる事業は、試作品開発・新サービス開発・販路拡大など多岐にわたり、助成限度額や助成率は都道府県ごとに異なります。
申請・採択後は、ファンド運営管理法人(都道府県の中小企業支援機関等)から助成金が支給されます。
全国で利用可能ですが、詳細な条件や公募スケジュールは各地域の実施機関で確認しましょう。
地域中小企業応援ファンドについては、独立行政法人 中小企業基盤整備機構のHPから確認いただけます。
地方別に使える制度も要チェック
全国的に使える補助金や助成金制度もあれば、各地方で独自の制度が用意されていることもあります。地方ごとに利用できる創業支援制度は、全国一律の補助金や助成金とは異なり、地域の産業構造や人口動態、行政の重点政策などに応じて多様な内容が設計されています。
特に地方では創業者を増やそうと取り組んでいるケースも多く、ただ金銭が受給できるだけでなく一定の手数料や金銭的な負担を軽減する仕組みが設けられていたりもします。
こうした地域支援を活用するには、まず自治体が提供する面談・セミナー・専門家相談などのプログラムに参加すると良いでしょう。
そこで自治体独自の制度について知ることができますし、有力なコネが構築できる可能性もあります。
補助金や助成金を活用するときの注意事項
補助金や助成金は、会社設立時や創業期の資金調達手段としても有効ですが、活用にあたって注意すべき点もあります。
|
申請要件や公募期間の確認 |
各制度には、対象となる事業内容、企業規模、設立からの年数など細かな要件が設けられている。募集期間も限定的なことが多く、締切を過ぎると申請はできない。必ず公式サイトで最新情報を確認し、自社が条件を満たしていることをチェックする。 |
|---|---|
|
後払いが原則 |
多くの補助金・助成金は、事業を実施したあとに支給される。入金されるまでには時間がかかるため、事前に必要な資金をどう確保するか、資金繰りの計画を立てておく必要がある。 |
|
使途や対象経費の制限 |
使える経費や対象となる支出は厳格に定められている。対象外の支出に充ててしまった分については支給が認められなかったり、返還を求められたりすることもある。 |
|
申請や報告手続きの負担が大きい |
申請時には事業計画や各種証明書類の提出が求められ、採択後も定期的な報告や実績確認が必要。書類の不備や遅延は支給遅れや不支給の原因となるため、余裕を持って準備し、正確な記録・報告を心がける。 |
|
税務処理も忘れない |
補助金や助成金は課税されることが多いため、税務処理も適切に行う。会計処理や申告に関しては税理士に依頼する。 |
これらの注意点を踏まえた上で活用について検討すること、そして申請をするなら期間に余裕を持ち計画的に進めることを意識してください。
投稿日:2025/7/11
高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。
-
まずはお気軽に無料相談
9:00~18:00(平日)