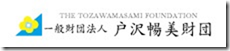消費税の歴史について
~消費税の歴史について~
今ではすっかり定着している消費税ですが、1989年(平成元年)に導入された時は世間で大
騒ぎだったのを覚えています。
所得税は累進課税(所得が高いほど税率が高い)ですが、消費税は逆進性(所得の低いほど
負担割合が高い)といわれ、学生だった私にとってはとても負担感がありました。消費税
が導入されてもお小遣いの額は増えませんでしたし...。
「消費税がなぜ導入されたか」
戦後シャウプ勧告により、所得税を税制の根幹に据え、基礎控除額を引き上げて負担の軽
減を図ると同時に、その減収分は高額所得者へ富裕税として課税されました(国税庁ホー
ムページより)。
その後、経済・社会の変化により、給与所得に税負担が偏ってきました。
税制全体の公平性の確保、個別間接税の問題点の解決、高齢化社会への対応が消費税導入
の理由とされています(租税研究会資料より)
「消費税率の推移(事業者免税点、簡易課税制度の適用上限)」
・1989年(平成元年)4月1日~ 消費税率 3% ※事業者免税点(3,000万円)
※簡易課税制度の適用上限(2億円)
・1997年(平成9年)4月1日~ 消費税率 5%
・2004年(平成16年)4月1日~ ※事業者免税点(1,000万円に引き下げ))
※簡易課税制度の適用上限(5,000万円に引き下げ))
・2014年(平成26年)4月1日~ 消費税率 8%
・2019年(令和元年)10月1日~ 消費税率 10%(軽減税率8%)
「インボイス制度の導入」
2023年(令和5年)10月1日よりインボイス制度が導入されました。
消費税が導入される前、1987年に中曽根内閣が「売上税法案」を提出しましたが、廃案に
なりました。このときインボイス制度が採用される予定だったようです。
消費税導入の際には多くの反対が予想されたことから、インボイス制度導入が見送られた
といわれています。インボイス制度が導入されなかったことから、「益税」という問題も
生じました。
「益税」とは消費者が事業者に支払った消費税のうち、納税されずに事業者の手元に残る
(利益となる)部分をいいます。
今回のインボイス制度は消費税導入時から考えられていたことなのですね。
インボイス登録を促すために、様々な特例を設けていた理由がわかる気がします。
ちなみに国税庁によると、インボイス制度は、
「税率が複数あっても、事業者の方が消費税を正確に納めていただけるように、消費税の
金額等を書いた請求書・領収書等(インボイス)を基に計算する仕組みです。」とのこと
です。益税の解消も大きな目的のようです。
さて、財務省のウェブサイトには、一般会計税収の推移が掲載されています。
1989年度(平成元年度)には3.3兆円だった消費税(一般会計税収:54.9兆円)ですが、2024年
度(令和6年度)には24.3兆円(一般会計税収:73.4兆円)となっています。
今や消費税は税収の30%以上を占めています。
所得税(20.1兆円)や法人税(18.1兆円)をも上回っており、少子高齢化社会において益々
消費税の重要性が高まっているようです。
課税の三原則は「公平」「中立」「簡素」といわれています。
消費税は上記の原則のうち、どれを満たしているのかと考えてみたりしています。
皆さんはどう思われますか。
投稿日:2025/8/8
高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。
-
まずはお気軽に無料相談
9:00~18:00(平日)