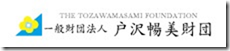令和7年度税制改正によって結局どうなる?基礎控除等の概要と実務ポイント
今回は令和7年度税制改正について、分かりやすくポイントをまとめてみました。
1) 基礎控除の大幅引き上げ
従来48万円だった基礎控除額が、一律+10万円引き上げられ58万円に増額
さらに合計所得金額132万円以下の場合には、控除額が最大+37万円上乗せされ、合計で95万に
合計所得金額132万円以下 : 95万円(改正前:48万円)
合計所得金額132万円超336万円以下 : 88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得金額336万円超489万円以下 : 68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得金額489万円超655万円以下 : 63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得金額655万円超2,350万円以下 : 58万円(改正前:48万円)
→ 結果として、従来は「103万円の壁」で課税が始まっていたところ、実質160万円まで税金ゼロになるなど、扶養されるパートタイマー労働者等への影響が大きくなります。
2) 給与所得控除の底上げ(パートタイマーや若手従業員に優しい設計)
給与収入190万円以下の従業員について控除の最低保障額が従来の55万円から65万円に
→ 給与所得が増えるにつれて課税対象が減り、特にパートタイマー労働者の手取り増が期待できます。
3)「特定親族特別控除」新設(大学生世代の扶養に配慮)
19~22歳で年収123万円以下の大学生等の子を扶養している場合、1人につき最大63万円控除される新制度が創設されました。
控除額は子の所得額に応じて段階設定(61万円・51万円…)。家計負担や手取り額に影響。
→ 社員に大学生家庭が多い場合、会社の年末調整書類や説明にこの制度を反映する必要があります。
4) 扶養控除等の所得要件の引き上げ(控除対象が広がる)
配偶者・扶養親族・ひとり親の子どもの所得条件が48万円 → 58万円に緩和されました。
勤労学生控除なども同様に75万円 → 85万円と要件が引き上げ。
→ 対象範囲が広がり、控除対象を申告できる社員が増える可能性があります。
●押さえておくべき実務ポイント
◇ 年末調整の変更
令和7年12月の年末調整から、改正後の基礎控除・給与所得控除が適用されます。
それまでの源泉徴収税額との差額を精算する必要があるため、12月は特に注意!
◇ 書類と申告の更新
扶養控除等(異動)申告書に、特定親族特別控除の欄が追加されます。制度導入に合わせて書式変更が必須です。
◇ 従業員への周知がカギ
「103万円ではなく160万円まで課税されない」と説明すれば、パートタイマー増員やシフト交渉でも安心感を提供できます。
大学生世代の子を持つ主婦層への説明も重要です。
◇ 給与設計・採用戦略への応用
控除幅の拡大により、手取りを落とさない範囲での給与設定やシフト割り振りが可能に。
その分、人件費を抑えつつ従業員の満足度を高める工夫ができるチャンスです。
年末調整対応と書類整備を早めに進め、従業員への説明をしっかり行うことが重要です。これらの変更は、従業員の安心感やモチベーション向上に直結しますので、制度理解・対応準備をして、実務に活かしていきましょう!
詳細はこちら
財務省HP
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_01.htm
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01
投稿日:2025/8/25
高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。
-
まずはお気軽に無料相談
9:00~18:00(平日)