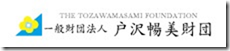返済不要の事業資金|補助金と助成金の特徴や違いについて解説
事業の成長や雇用環境の改善に取り組むなら、補助金や助成金といった仕組みを活用して資金調達することも検討してみましょう。
どちらも返済が不要で事業者の活動を支援する制度といえますが、調達規模や審査方式など違いも多く存在します。
最終的には個別の要件を詳細に見ていくことが求められますが、ここでは補助金および助成金の大枠を確認していきましょう。
事業者向けの支援金制度の概要
補助金と助成金は、国や地方自治体が事業者の特定の取り組みを支援するために設けた、返済不要の支援金制度ということができます。
融資とは異なり、一定の条件を満たせば借金を負うことなく事業資金を調達できる点が最大の特徴です。
これらの制度は政策目標の実現手段として位置づけられており、経済活性化や雇用促進、技術革新の推進など、社会全体の発展に寄与する事業活動を後押しする役割を担っています。事業者としても、新規事業の立ち上げや設備投資、人材育成などの資金源として使えるためメリットは大きいでしょう。
制度利用の基本的な流れとしては、①事業者は所定の要件に基づいて申請を行う、②審査を経て採択される、③事業実施後に支給を受ける、という仕組みになっています。そのため前もって資金調達ができるわけではないという点は理解しておく必要があります。
また、両制度とも税金や保険料を財源としているため、厳格さ・適正性を重視して運用がなされています。
事後の監査や報告義務も伴いますし、事業者側は適切な記録管理と報告の体制を整えなくてはなりません。
補助金と助成金の主な違い
両制度は類似する性格を持ちながらも、運営方針や制度設計において違いが存在します。
事業者がいずれかまたは両方の制度を有効活用するには、これらの特徴をよく理解することが必要です。
管轄省庁・財源が違う
事業者が申請する際の窓口、そして財源も異なります。
- 補助金・・・経済産業省や中小企業庁、都道府県・市区町村などが管轄し、国税や地方税を財源とする。
- 助成金・・・厚生労働省の都道府県労働局が管轄し、雇用保険料を主な財源として運営されている。
この財源の違いは制度の目的にも反映されており、補助金は「経済政策の推進」に重きが置かれています。
産業振興や地域活性化といった政策目標を達成するため、革新的な技術開発や新規市場の開拓、生産性向上につながる設備投資などが重点的に支援されます。
助成金は「雇用政策の実現」に重きが置かれ、雇用の安定化や労働者のスキルアップ、働きやすい職場環境の整備などが支援対象の中心となります。
資金の支給規模が違う
支給額については補助金の方が大きい傾向にあり、数百万円から数億円の範囲で設定されることが多いです。
対して助成金は数十万円から100万円程度が一般的です。
この違いは支援対象となる事業活動の規模に起因していると考えられるでしょう。補助金だと大型の設備投資や研究開発、新事業の立ち上げなど、まとまった資金を必要とする取り組みを対象とすることが多いため、支給額も相応に高額となります。経費の適用範囲も比較的広く、設備費や人件費、外注費など多岐にわたる費用が対象となるケースが多いです。
助成金は従業員の能力開発や雇用促進など、比較的小規模な取り組みを支援対象としているため、支給額は控えめに設定されています。
しかし、継続的な取り組みに対しては複数年にわたって支給を受けられる場合もあり、その場合は長期的な支援が期待できます。
審査方式や受給難易度が違う
いずれも、申請した事業者すべてが受給できるとは限りません。そしてその際の審査方式においても大きな違いがあります。
補助金は提案の優劣によって採択を決定する「コンペ方式」を採用していることが多く、採択率は制度によって異なるものの、50%を下回ることも珍しくありません。
事業計画の独創性や実現可能性、地域経済への波及効果など、多角的な評価基準をクリアする必要があります。さらに、その基準をクリアしていることを示すために詳細な事業計画書の作成が求められ、技術的な新規性や事業性、将来的な波及効果なども総合的に見られます。
助成金は要件充足型の制度設計となっており、条件を満たせば基本的には給付を受けられます。
就業規則の整備や雇用保険の適用など、基本的な労務管理体制が整っていれば申請可能なケースが多く、補助金に比べると受給しやすいといえるでしょう。
申請期間が違う
申請期間については、補助金は年度予算に基づいて数週間から数ヶ月程度の限定的な公募期間が設定されることが多く、タイミングを逃すと次年度まで申請機会がないケースが多いです。また、予算消化により早期に締め切られることもありますので、次の点には注意しましょう。
- 公募開始の情報収集を定期的に行うこと
- 申請書類の事前準備を進めておくこと
- 予算枠を考慮して早期申請を心がけること
一方、助成金は通年で申請できるものが多く、時間的制約は比較的緩やかです。ただし、予算上限に達し次第締め切りとなる可能性もゼロではないため、計画的に取り組むことが推奨されます。
効果的な活用方法
融資やその他の資金調達手段と組み合わせて、補助金や助成金も活用すると良いでしょう。
補助金か助成金か、とどちらか一方に限定する必要もありません。利用できる仕組みを複数組み合わせて活用すると、より大きな効果を得ることができます。
具体的な制度についてはその時々で最新情報にアクセスすることが重要ですが、例としては次のものが挙げられます。
| 補助金 | ものづくり補助金 | ・革新的な設備投資やサービス開発を支援
・中小企業等の生産性向上を目的とする |
|---|---|---|
| IT導入補助金 | ・ITツール導入による業務効率化を支援
・幅広い業種で活用可能 |
|
| 中小企業省力化投資補助金 | ・人手不足解消のための省力化製品導入を支援
・2025年に一般型が新設された |
|
| 助成金 | キャリアアップ助成金 | ・非正規労働者の正社員化や処遇改善を支援
・賃金規定の改定、賞与・退職金制度導入なども対象 |
| 人材開発支援助成金 | ・職業訓練の実施に対して経費や賃金の一部を支援
・社内研修、外部講習、OJTなど対象は幅広い |
|
| 雇用調整助成金 | ・経済状況悪化で雇用維持が困難な事業主を支援
・雇用維持のための休業、教育訓練、出向など |
なお、両制度とも過去の法令違反や不正受給が判明した場合、申請が受理されない可能性があります。
特に同種の制度において不正行為があった場合、長期間にわたって申請資格を失うリスクがありますので注意してください。
また、制度の新設や改正は頻繁に行われるため、関連省庁のWebサイトをチェックしたり専門家に相談したりするなどして、定期的に情報をアップデートしましょう。
投稿日:2025/10/9
高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。
-
まずはお気軽に無料相談
9:00~18:00(平日)