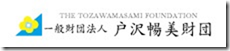消費税の種類を理解しよう
物価高や米国の関税措置を受け、消費税減税の声を日々のニュースで多く聞きます。
消費税減税に向けた提案としては、「食料品の消費税率を原則1年間に限りゼロとする。」「食料品の消費税率を時限的にゼロにする。」
「消費税率を一律5%に引き下げる。」など様々あります。そこで今回はそもそも消費税ってどんなものがあるかおさらいしましょう。
消費税は大きく4つに分類されます。
(1)課税取引 (2)不課税取引 (3)非課税取引 (4)免税取引
「(1)課税取引」の定義として①~④があります。
①:国内において行う取引
②:事業者が事業として行うもの
③:対価を得て行うもの
④:資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供
基本的に私たちが目にするほとんどの取引がこちらの(1)に該当します。
「(2)不課税取引」は「(1)課税取引」の定義に当てはまらない取引になります。
例としては
①給与・賃金の支払い:雇用契約であるため事業には該当しない
②寄付金・祝金・補助金:一般的に「対価」として授受されるものではない
③保険金:保険事故に対して支払われるものであって、「対価」ではない
④出資に対しての配当:株主の地位に対して支払われるもので、「対価」ではない
⑤損害賠償金:一般的に「対価性」がないといわれている
⑥盗難・減失:資産の譲渡などには該当しない
⑦自家用車の売却:個人での車の売却は、事業者が事業として行うものではない
⑧国外取引:その譲渡又は貸付け、役務の提供が行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。
「(3)非課税取引」は「広く公平な負担」という消費税の性質になじまないものや、社会政策上の配慮によって課税が適さない取引については非課税取引となります。
例としては
①社会保険医療
②行政サービス手数料
③学校の授業料や入学金
④教科書の購入費用
⑤土地の売買や貸付
⑥住宅の貸付
⑦株の売買(手数料は課税対象)
⑧訪問介護サービスなどの費用
⑨預金や貸付金の利子
非課税取引は上記のように極めて限定的なものとなっています。
不課税取引と似ていますが、不課税取引は消費税の課税要件を満たさないのに対し、
非課税取引は、課税要件を満たしても社会政策上の配慮などから課税が適当でないと判断された取引を指すのです。
「(4)免税取引」は一定の要件を満たした場合に、資産の譲渡などについて課税される消費税が免除されるものになります。
例としては
①外国人観光客向けの免税店
②外国貨物の譲渡または貸付
③国際輸送
④国際通信
⑤国際郵便
非課税取引と免税取引は似ていますが、消費税額の計算上大きな違いがあるので注意しましょう。
具体的には、取引のために行った仕入れについて仕入税額を控除できるかどうかの違いです。
免税取引の場合、原則として仕入れにかかる消費税額が控除されます。
最後に
不課税・非課税・免税と結局課税0円ってことではないの?と思うかもしれませんが
課税売上割合の計算においてその取扱いが異なってきます。
つまり同じ0円でも種類によって納付額が異なります。
今回は消費税の大まかな分類についてご説明しましたが、消費税にはもっと様々な論点がございますので
興味のある方はぜひ弊法人までご連絡ください。
投稿日:2025/7/28
高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。
-
まずはお気軽に無料相談
9:00~18:00(平日)